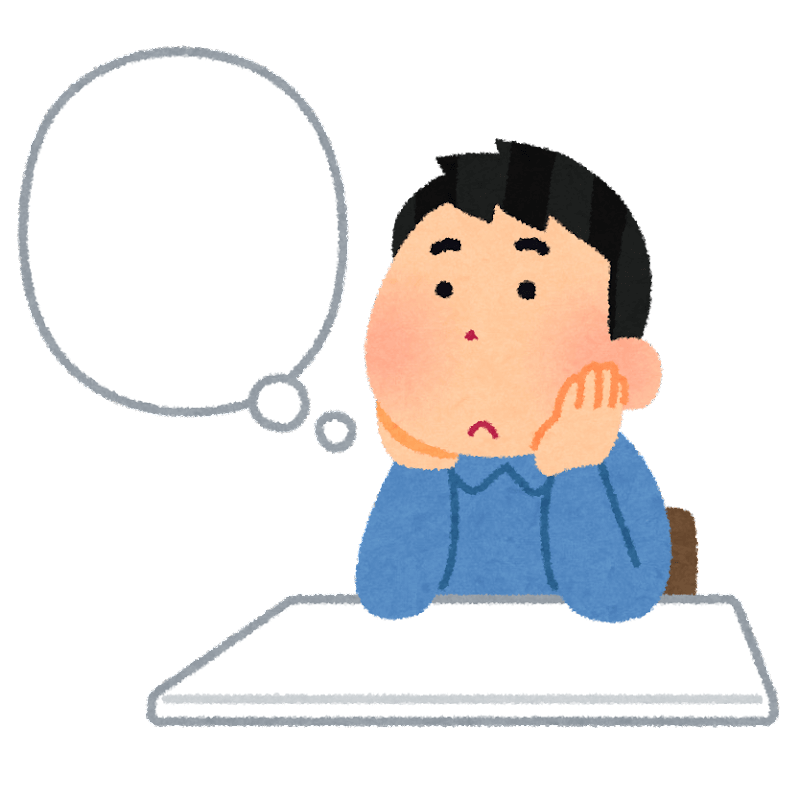
「だ・である調」と「ですます調」の特徴が知りたい。
「だ・である調」と「ですます調」はどう使えばいいの?
「だ・である調」と「ですます調」の一覧を見たいな。
こういった疑問や悩みを解決する記事です。
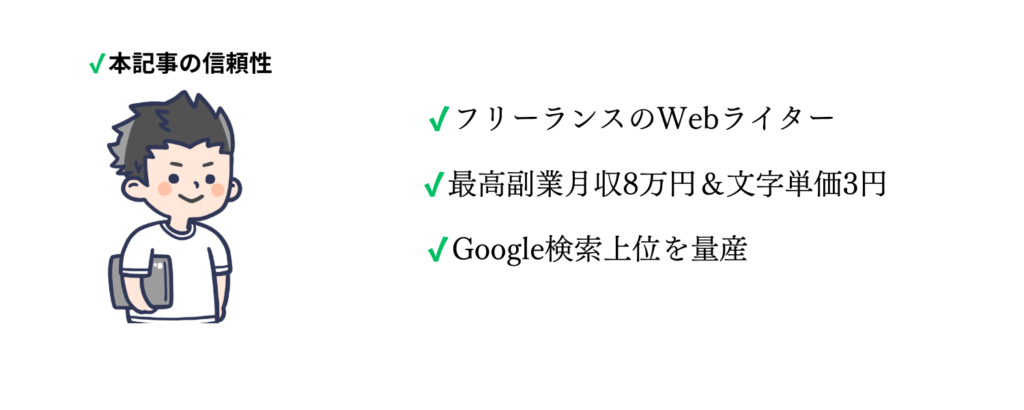
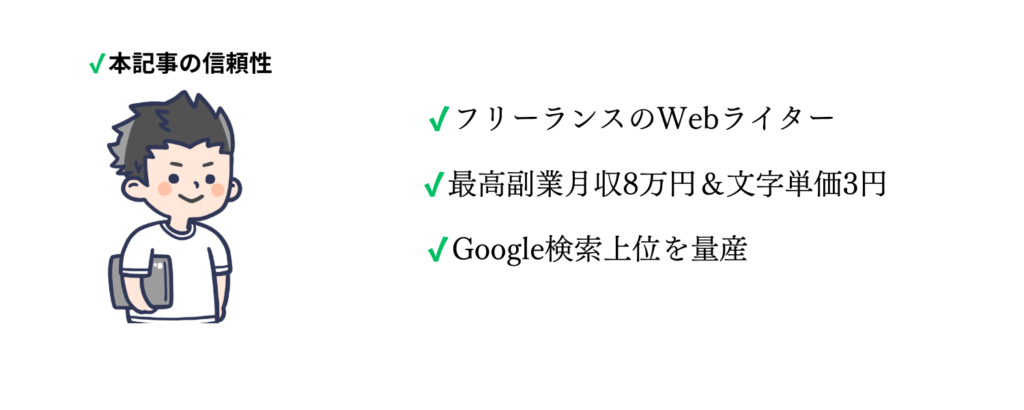
本記事では「です・ます調」「だ・である調」の特徴や使い方などを詳しく解説しています。
この記事を読めば「だ・である調」「ですます調」の使い方を理解できます。
「だ・である調」「ですます調」について詳しく知りたい人は、最後まで読んでみてください。
「だ・である調」と「ですます調」の違いとは?
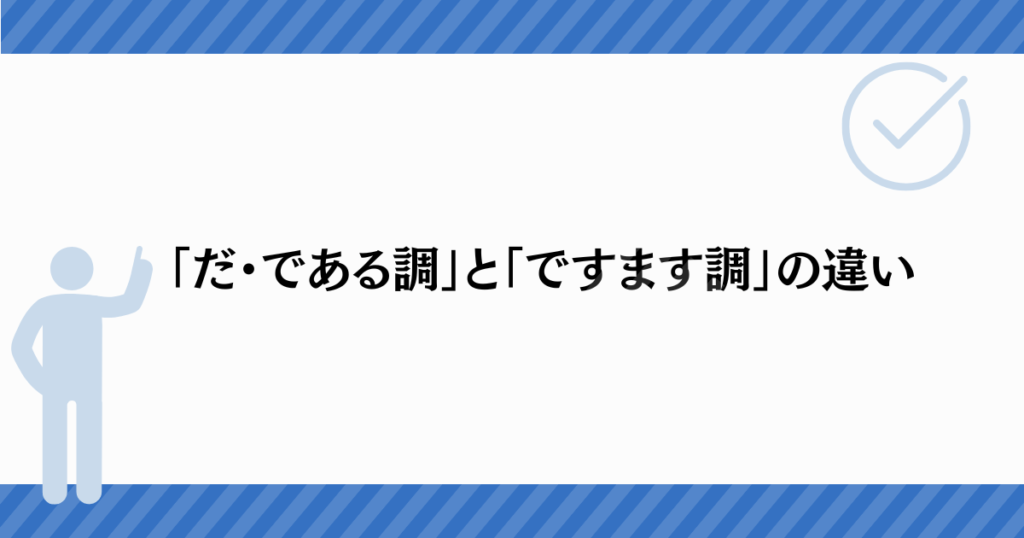
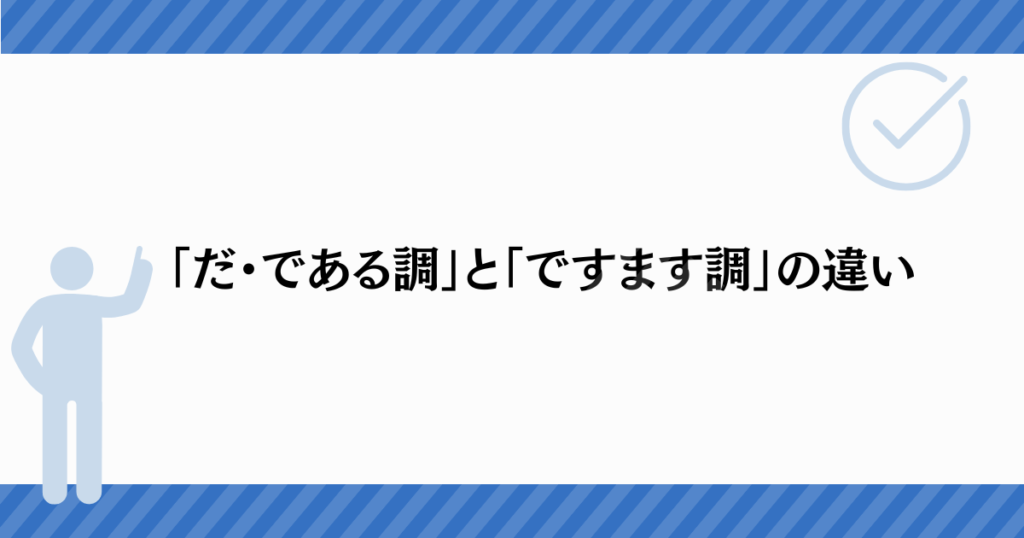
「だ・である調」と「ですます調」は、日本語の話し方や書き方の違いです。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
だ・である調の特徴
だ・である調は、公式な文章や論文などでよく使われる言い方です。
文章がすっきりしていて、強い言い方になるのが特徴です。
例えば「これは本である」と書くと、はっきりと「これは本だ」といっているように聞こえます。
だ・である調は威厳を感じる言葉遣いなので、説得力を出したいときによく使われます。
ですます調の特徴
ですます調は、日常の会話やメールでよく使われる言い方です。
この言い方は相手に対して丁寧で、物腰が柔らかい印象を与えます。
例えば「今日は学校が楽しかったです」というと、聞いている人に対して敬意を示しつつ、自分の感じたことを伝えられます。
である調は悪くいうと「偉そう」な印象を与える一方で、ですます調は礼儀正しい言葉遣いです。
だ・である調の一覧表


だ・である調の種類は以下のとおりです。
| 語尾 | 例文 |
|---|---|
| だ | Webライターだ |
| である | Webライターである |
| と言える | Webライターと言える |
| とされている | Webライターとされている |
| だそうだ | Webライターだそうだ |
| だろう | Webライターだろう |
| だろうか | Webライターだろうか |
| をしてほしい | Webライターをしてほしい |
| をしてみよう | Webライターをしてみよう |
| らしい | Webライターらしい |
| のようだ | Webライターのようだ |
| とのことだ | Webライターとのことだ |
| ではない | Webライターではない |
| かもしれない | Webライターかもしれない |
| のはずだ | Webライターのはずだ |
ですます調の一覧表
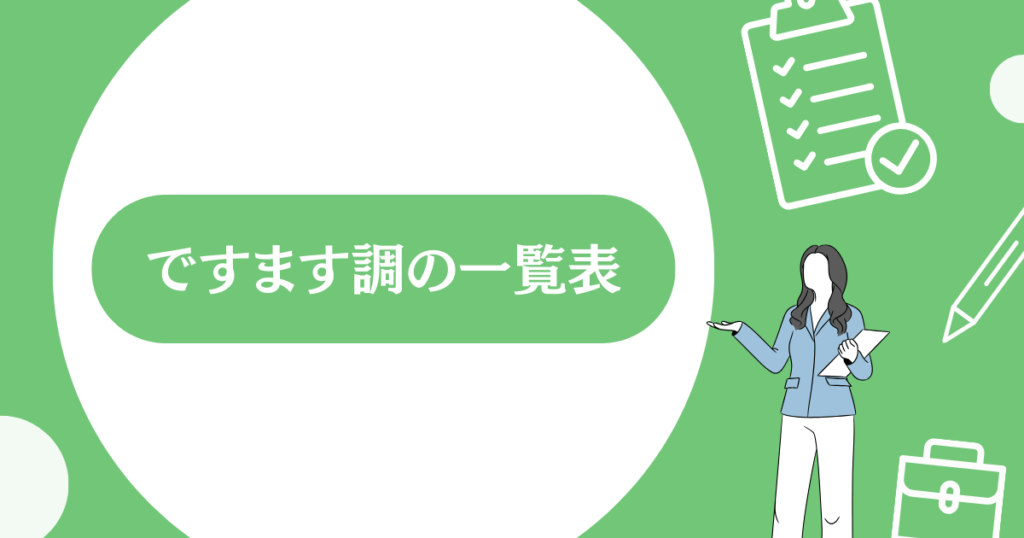
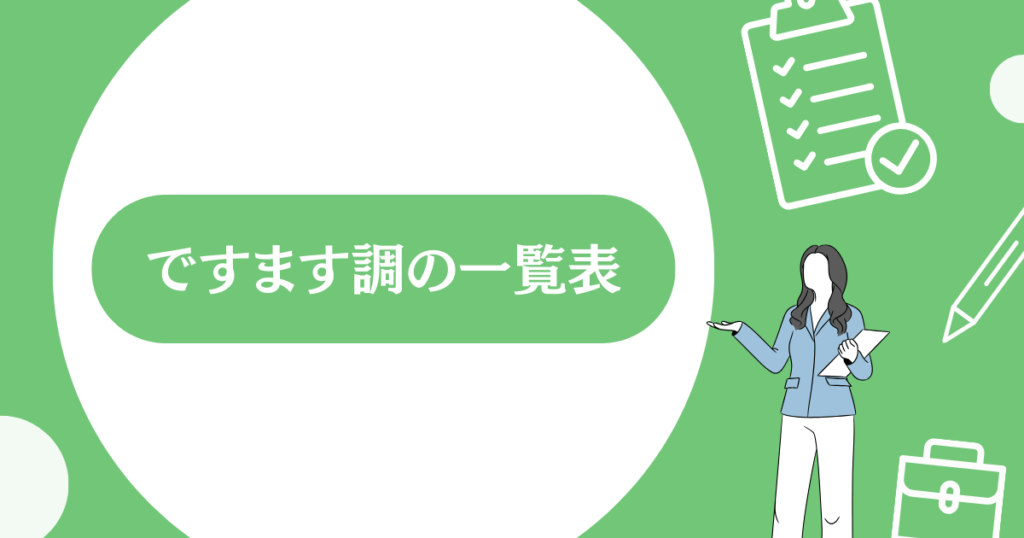
ですます調の種類は以下のとおり。
| 語尾 | 例文 |
|---|---|
| です | Webライターです。 |
| ます | Webライターをしています。 |
| されています | Webライターをされています。 |
| 言えます | Webライターと言えます。 |
| なはずです | Webライターなはずです。 |
| でしょう | Webライターでしょう。 |
| ですか | Webライターですか? |
| でしょうか | Webライターでしょうか? |
| してください | Webライターをしてください。 |
| しましょう | Webライターをしましょう。 |
| のようです | Webライターのようです。 |
| らしいです | Webライターらしいです。 |
| だそうです | Webライターだそうです。 |
| とのことです | Webライターとのことです。 |
| ではありません | Webライターではありません。 |
| でした | Webライターでした。 |
| していました | Webライターをしていました。 |
| かもしれません | Webライターかもしれません。 |
| ですね | Webライターですね。 |
だ・である調の使い方と読み手への印象


ここでは、だ・である調の使い方と読み手への印象を解説します。
だ・である調の基本的な使い方
だ・である調を効果的に使うためには、文末に注意を払いましょう。
「である」や「だ」などの語尾は、文体の特徴を示すものです。
上記を適切に使うことで、文の終わりに締めくくりを持たせられます。
例えば「彼の提案は効果的である。」といった文で「である」が効果的に使われています。
倒置と箇条書きを使った応用的な使い方
だ・である調を使うときは、文体が単調にならないよう工夫することも重要です。
その1つの方法として、倒置や箇条書きを活用するのが効果的です。
例えば「彼は熱心な学生である。」という文を「熱心な学生である、彼は。」と倒置することで、文章に変化をつけられます。
箇条書きは情報を整理しやすく、読み手にとってもわかりやすい方法です。
長い説明文を箇条書きにすることで、情報をパッと見で理解できます。
だ・である調の論文やレポートでの使い方
だ・である調は、論文やレポートの作成においても非常に役立ちます。
これらの文書では情報を明確に伝えることが求められるので、シンプルな表現が重要です。
例えば「私はこの仕事に適している」「この実験は重要な結果を示している」というように、事実を明瞭に伝えたいときに使います。
だ・である調を使うことで、自分の考えや結果を強くはっきりと伝えられます。
ですます調の使い方と読み手への印象
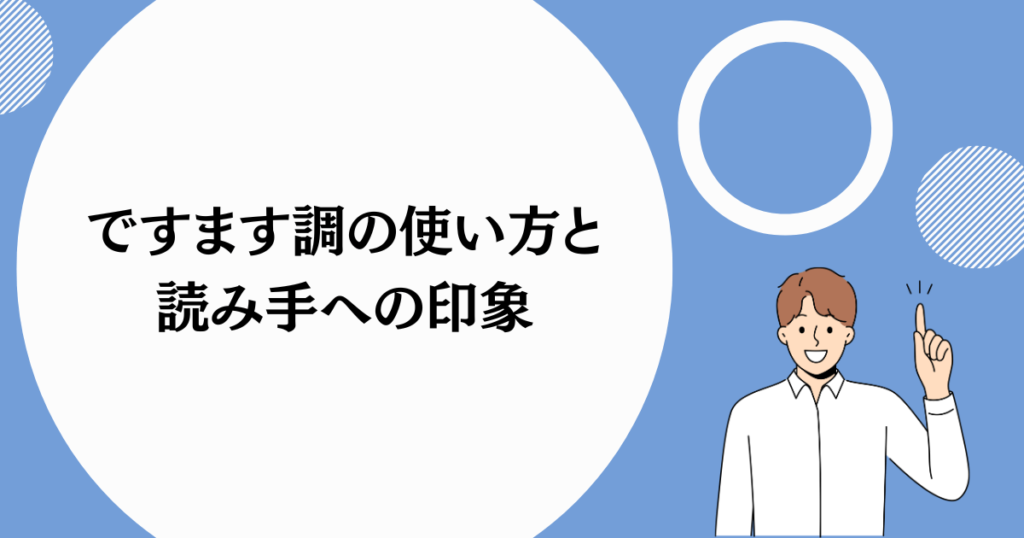
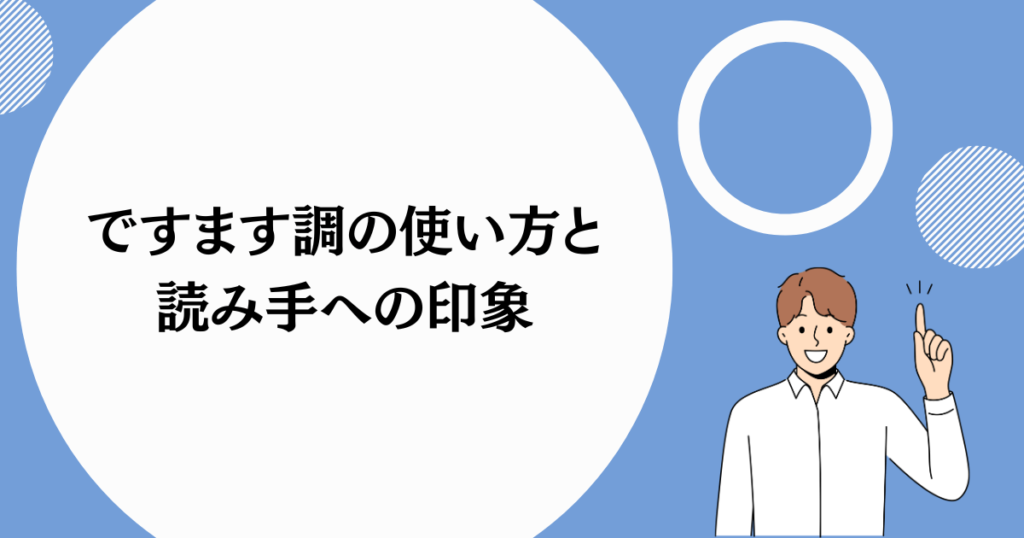
ここでは、ですます調の使い方と、読み手への印象について解説していきます。
ですます調の基本的な使い方
「ですます調」は丁寧な表現を特徴としており、読み手に対する敬意を示すのに適しています。
文末の「です」「ます」は、その丁寧さを示す重要な要素です。
また、敬意を示すためには尊敬語や謙譲語との組み合わせも大切です。
読者に対する尊重を示すために「お願い申し上げます。」などの表現が使われます。
ですます調で語尾を連続して使うと稚拙に見える
ですます調で語尾を連続して使うと文章が単調かつ稚拙に見えるので、注意が必要です。
一例を見てみましょう。
語尾の連続が3回続くのはNGです。
3回連続で続くと、単調で稚拙な文章に見えるからです。
幼稚な印象を与えないためにも、語尾を3回連続で続けるのは避けるべきです。
上記のように語尾が連続することで、アホっぽい印象を受けると思います。
稚拙な印象を避けるためにも、バリエーションを持たせる工夫が必要です。
ですます調のビジネス文書やWebコラムでの使い方
ですます調は、丁寧な表現が求められるビジネス文書やWebコラムでよく使われます。
ビジネス文書では、商品やサービスの説明・お客様へのメッセージ・プロモーション文などにですます調が適しています。
読者への説明や提案を丁寧におこなうために、この文体を使いましょう。
また、Webコラムやブログ記事では、読者との対話が大切です。
親しみやすい印象を持たせるためにもですます調を活用し、読者とのコミュニケーションを円滑にしましょう。
「だ・である調」と「ですます調」のメリット・デメリット
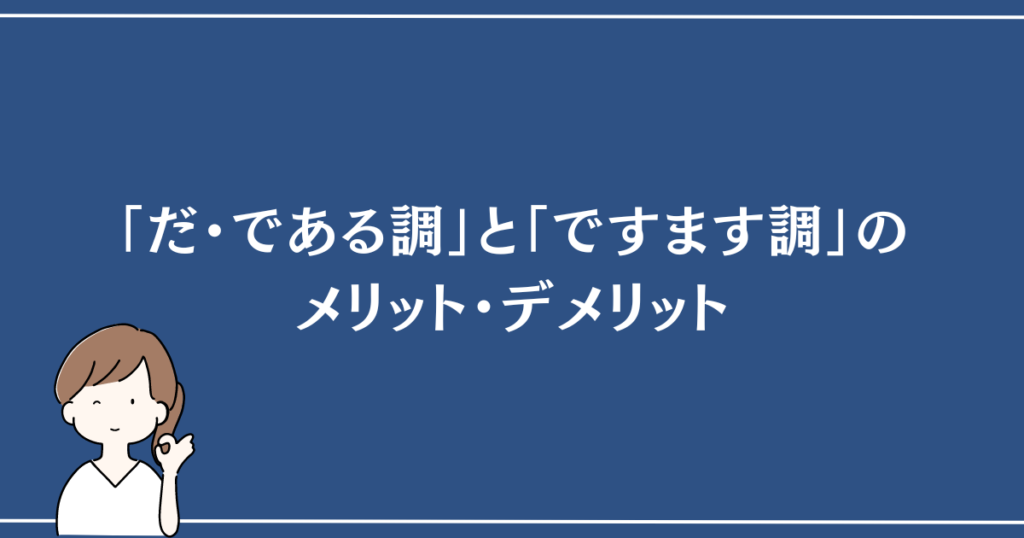
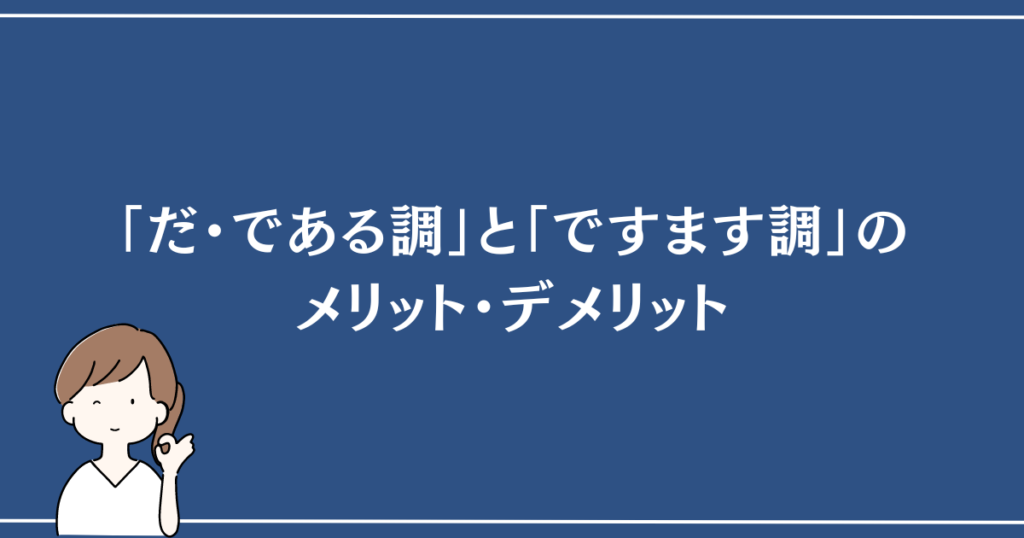
「だ・である調」と「ですます調」それぞれのメリットとデメリットについて解説していきます。
だ・である調のメリット:説得力と簡潔さ
だ・である調のメリットは、その説得力と簡潔さです。
この文体を使うことで、情報を明確かつ効果的に伝えることができます。
ビジネス文書やレポートでは、要点を的確に伝える必要がありますが、その点で「である調」は効果的です。
例えば、プレゼン資料で「新製品は市場で競争力をもっています」というより「新製品は市場で競争力をもっている」という表現のほうが力強い印象があります。
また、シンプルな表現は読者にわかりやすく、情報の取り入れやすさを提供します。
短時間で多くの情報を伝える必要がある場合、この文体は便利です。
だ・である調のデメリット:硬い印象を与える
だ・である調は大切な点をはっきり伝えることができる反面、硬い印象を与えます。
友達や家族との会話では少し距離を感じさせることがあるので、場面によっては使いにくいです。
どちらの言い方も場面に合わせて上手に使うことが大切です。
ですます調のメリット:丁寧さと読者への共感
ですます調のメリットは、丁寧さと相手に対する敬意を示せることです。
特に、顧客対応やビジネスメール、Webコンテンツでの使用においては、丁寧な態度で対応することが大切です。
例えば、お客様へのメールで「ご不明点がございましたらお気軽にお知らせください」という表現は、丁寧かつ敬意が伝わります。
ビジネスシーンでは、ですます調で対応するのが一般的です。
ですます調のデメリット:与える印象が弱い
ですます調は丁寧で礼儀正しい言葉ですが、少し柔らかすぎて、大事なことをはっきり伝えにくい場合があります。
特に、重要な報告や議論のときには、相手に十分に強い印象を与えられないことがあります。
「だ・である調」と「ですます調」は、目的や読者に合わせて使い分ける


「だ・である調」と「ですます調」は、目的や読者に合わせて使い分けるのが効果的です。
コンテンツの目的
コンテンツの目的に合わせて文体を選びましょう。
情報をシンプルに伝えたい場合や、説得力を持たせたい場合は「である調」が適しています。
一方、読者への共感や丁寧な対応が必要な場合には「ですます調」が適しています。
読者
読者の属性や期待に合わせて文体を選びましょう。
ビジネス文書では、相手の業界や地域によっても適切な文体が異なります。
また、特定の世代や文化に合わせた表現を選ぶことも重要です。
文脈
文脈によっても文体の選択が変わります。
例えば、フォーマルな報告書では「である調」が一般的ですが、会話形式のWeb記事では「ですます調」が自然な表現になることがあります。
文脈を考慮し、読者に適した印象を与える文体を選びましょう。
コンテンツの内容
コンテンツの内容によって使い分けるのも効果的です。
冷静で客観的なトーンを求める場合は「だ・である調」が適していますが、親しみやすさや感情表現を重視する場合は「ですます調」が適しています。
コンテンツの内容を考慮し、使い分けましょう。
それに合わせて文体を選ぶことで、業界内での信頼性を高められます。
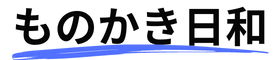

コメント